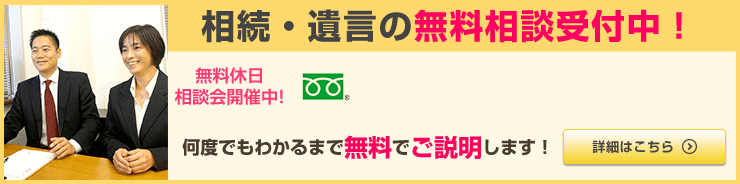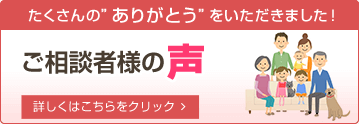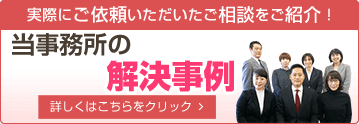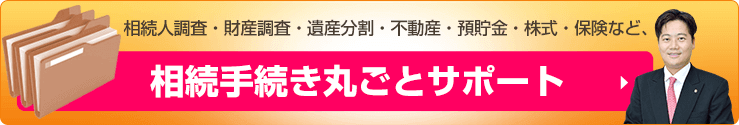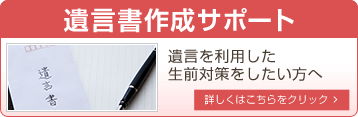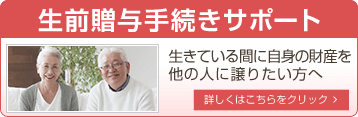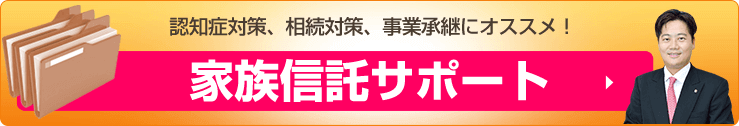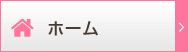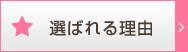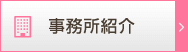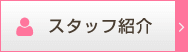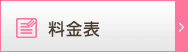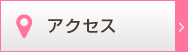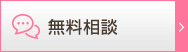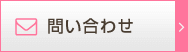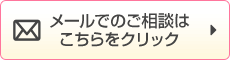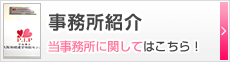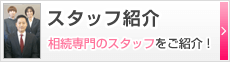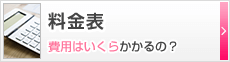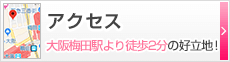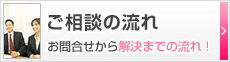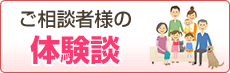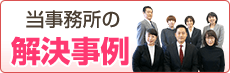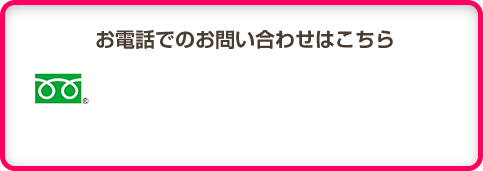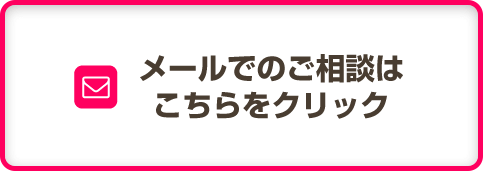相続財産目録を作ることについて
亡くなった人(被相続人)が遺言書とともに財産目録を残してくれていなければ、相続人が遺産を調査して相続財産目録を作成します。
わずらわしい作業ですが、資産と負債に分けて、わかりやすいものからリストアップしていきましょう。
相続財産目録が無ければ、そもそも遺産がどういう形でいくらあるかを相続人全員がわからないので、遺産分割の話し合いができません。
把握できている範囲でまず部分的な分割をおこない、後日遺産を全部把握できた後に最終的な分割(清算)をするというやり方もありますが、良い方法とは言えません。
正式な遺産分割協議書が無ければ、被相続人名義の預金の引き出しや、不動産の所有権移転登記などの手続きもできません。
また、相続税の申告が必要な場合、申告書には相続財産目録を添付する必要があります(相続税の申告と納付の期限は、相続開始後10ヶ月以内です)。
ですから遺産の調査と相続財産目録の作成はできるだけ早く済ませるようにしましょう。
遺産が多額かつ複雑で把握できないものもあり、調査するのに素人では手に負えない場合は、当所に依頼してみるのも一手です。
相続 花子
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。

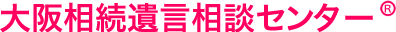
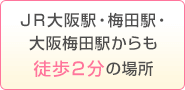
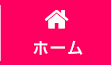
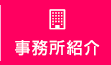

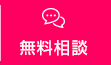


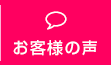


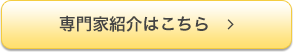
.png)
.png)
.png)