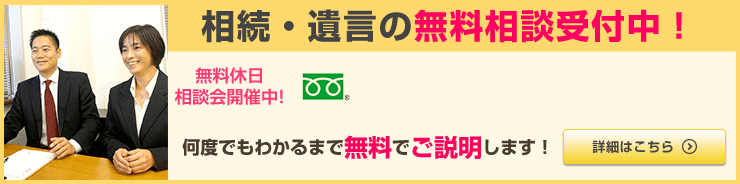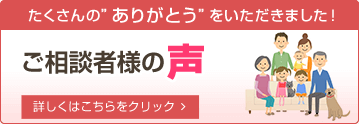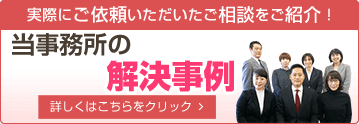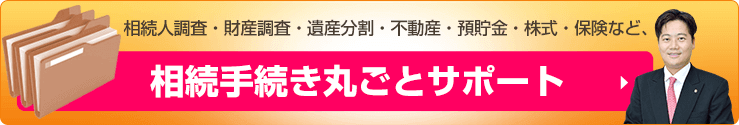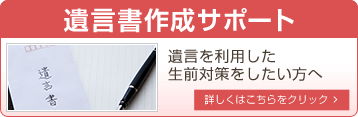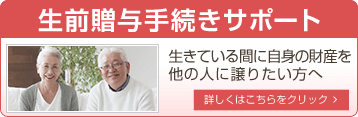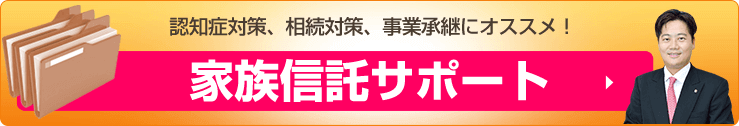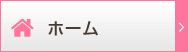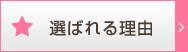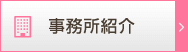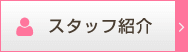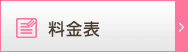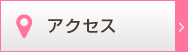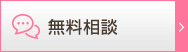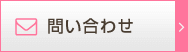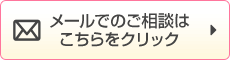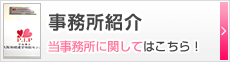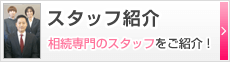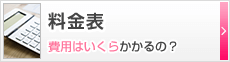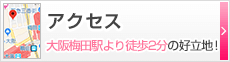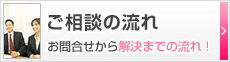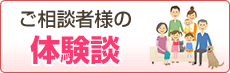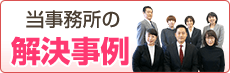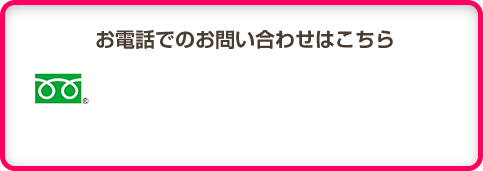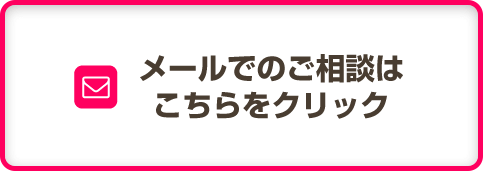家庭裁判所での遺産分割調停手続きの流れ

家庭裁判所での遺産分割調停手続きの流れ
相続人同士で遺産の分け方がまとまらないとき、家庭裁判所での遺産分割調停を利用できます。ここでは、その手続きの流れを分かりやすく説明します。
1. 遺産相続手続きの準備
まず、次の準備が必要です:
- 戸籍謄本を集める:被相続人と相続人全員の戸籍謄本を取得します。
- 遺産を調べる:預貯金、不動産、有価証券などの遺産を把握します。
- 相続人を確認する:法定相続人を特定します。
準備ができたら、相続人同士で遺産の分け方を話し合います。話し合いで解決できない場合、調停手続きに進みます。
2. 遺産分割調停の申立て
調停を申し立てる手順は次のとおりです:
- 調停申立書を作成する
- 必要書類を用意する(戸籍謄本、遺産目録、相続関係説明図など)
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する
- 手数料(収入印紙)を納付する
申立人は相続人の中から決めます。一人でも複数でも構いません。
3. 調停申立書の書き方
調停申立書には、以下の内容を記載します:
- 相続人全員の氏名と住所
- 申立ての趣旨(調停で決めてほしいこと)
- 申立ての理由(なぜ調停が必要なのか)
- 遺産の内容と価値
記入例:
遺産分割調停申立書
令和〇年〇月〇日
〇〇家庭裁判所 御中
申立人:〇〇 〇〇
住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
申立ての趣旨
被相続人〇〇 〇〇の遺産について、別紙遺産目録記載の財産の分割を求めます。
申立ての理由
1. 被相続人〇〇 〇〇は、令和〇年〇月〇日に死亡しました。
2. 相続人は、申立人のほか、別紙相続関係説明図記載のとおりです。
3. 遺産分割について話し合いましたが、意見がまとまりませんでした。
そのため、調停による解決を求めます。
添付書類
1. 戸籍謄本
2. 遺産目録
3. 相続関係説明図
4. 家庭裁判所での調停の進め方
調停の流れは次のようになります:
- 調停期日の通知:裁判所から調停の日時が通知されます。
- 調停への出席:指定された日時に家庭裁判所へ行きます。
- 調停の進行:調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを進めます。
- 複数回の調停:必要に応じて何回か話し合いを重ねます。
- 調停の結果:話がまとまれば調停成立、まとまらなければ不成立となります。
調停がうまくいけば遺産の分け方が決まります。うまくいかない場合は、裁判に進むこともあります。
5. 調停申立書作成時の注意点
- 名前や住所は正確に記入する
- 遺産の分け方について、具体的な希望を書く
- 調停が必要な理由を簡潔に説明する
- 遺産の内容と価値をできるだけ詳しく記載する
- 相続人全員の名前を漏れなく書く
専門的な内容で不安な場合は、弁護士や司法書士に相談するのもよいでしょう。
まとめ
遺産分割調停の流れは以下のとおりです:
- 相続の準備をする
- 相続人同士で話し合う
- 話がまとまらなければ調停を申し立てる
- 家庭裁判所で調停を行う
- 調停で遺産の分け方を決める
調停は、裁判所が間に入って話し合いをサポートしてくれる制度です。ただし、ある程度の時間と費用がかかります。また、専門的な知識が必要な場合もあるので、困ったときは法律の専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割は家族の問題でもあるので、できるだけ話し合いで解決できるよう努力することが大切です。しかし、どうしても解決できないときは、この調停制度を利用することを検討しましょう。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。

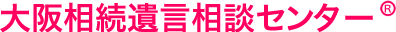
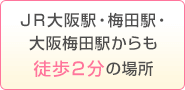
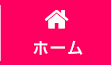
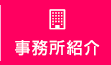

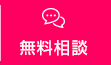


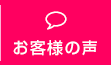


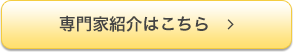
.png)
.png)
.png)